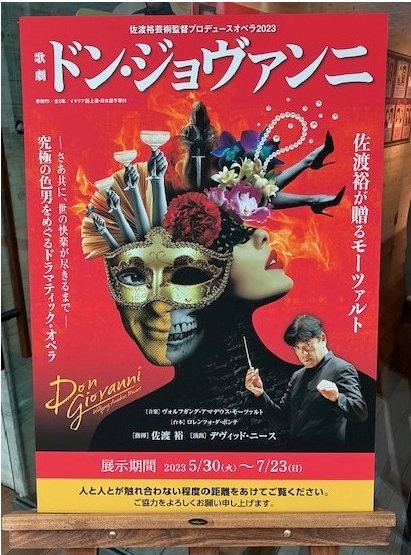「この名画はなぜ名画なのか」シリーズ
モナ・リザは、般若心経である。
いきなりトンデモ説のタイトルみたいですが、別にモナ・リザが仏教だと言っている訳ではありません(笑)。ダ・ヴィンチの膨大な手稿(=科学ノート)の存在を知ると、モナ・リザと手稿は不即不離の一体であることが理解できます。その手稿のエッセンスを凝縮して、誰にも受け入れやすい形にしたらモナ・リザになる、という趣旨です。両者の関係を膨大な大般若経と、それを260文字にダイジェストした般若心経の関係に見立てた、だけのことです。

なので絵を単独で切り離して、美術品として鑑賞して何らかの美を見出そうとしても、無理があるというものです。モナ・リザは文字こそ描き込まれていないけれど、着彩もされてダ・ヴィンチの思想を発信しています。ダ・ヴィンチの深奥を覗く小窓かもしれません。
それではモナ・リザの絵が伝えようとしている「教義」とは何でしょうか。ダ・ヴィンチは「絵画論」において、絵画は科学でなければならないことを一貫して語っています。また霊魂を完全否定して、「科学上の経験のないところに真の知識は生まれない」と断言します。つまり科学的世界観を描く技術こそが絵画である、ときっぱり定義しているのです。驚きますよねえ、まだ中世の迷信や祈りが幅を利かせて、全てを神の思し召しとしていた時代、ダ・ヴィンチは早くも人体解剖を行い、人間は母親の子宮から生まれ、人間の活動を支配するのは脳の働きであることをすでに知っていたのですから。彼こそは真のルネサンス人でした。


ではモナ・リザの絵に込められた科学性を、そのつもりで見ていきましょう。まずいちばん右奥の雪山です。雪は解けて湖へ、さらに川となって下流へと大地を削りながら蛇行するのを模式的に表しています。その水の流れとモナ・リザの胸像が重なっているのは決して偶然ではないでしょう。多くの人が指摘するように、地球を輪廻する水と人体の小宇宙を巡る血流が実は同じ原理である、という真理の表明でしょう。ダ・ヴィンチの雄大で洞察に満ちたコスモロジー(宇宙論)を視覚的にプレゼンしています。
また背後の峩々たる山並みは、僕の考えではイタリアにも多いカルスト地形で、海の生物が堆積してできた石灰質の隆起して浸食された表現です。ダ・ヴィンチは高い山にある貝やサンゴの化石に興味をもって、大地もまた輪廻していることに思いが及んだ先進的な地質学者でした。今で言うプレートテクトニクスです。なので山がおどろおどろしいのは、ダ・ヴィンチが終末思想を持っていたからなどという解釈は、全く間違いです。
背景の色合いについては、手前から遠くへ、緑から青、そして灰色へと変化して、空間の奥行きを感じさせます。これはダ・ヴィンチが発明した「空気遠近法」で、彼の受胎告知の作品でも使われる技法です。
さていよいよ、話をモナ・リザ本人の顔やポーズに移したいところですが、長くなったので次回に。僕はモナ・リザの座る空間の謎を自分で解明してみて、驚きを隠せませんでした(つづく)。
岩佐倫太郎 美術評論家/美術ソムリエ